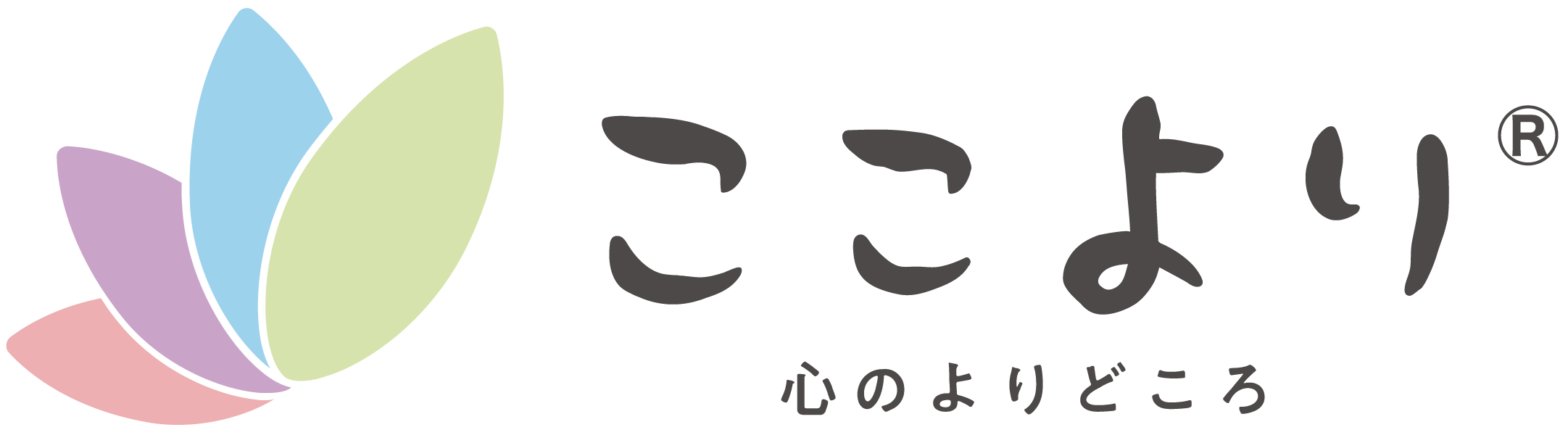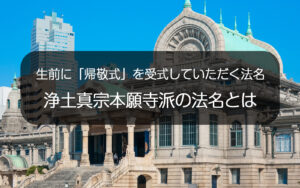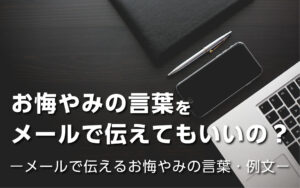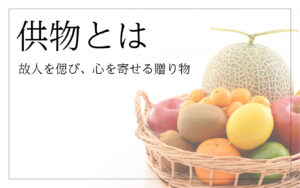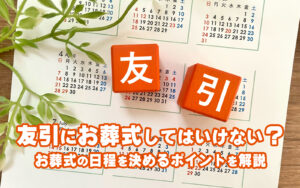慣わしについて
生前に「帰敬式」を受式していただく法名|浄土真宗本願寺派の法名とは
「法名」は仏法に帰依し、釈尊の弟子となった証として授かる名前です。
その法名は、生前に「帰敬式」を受式して、本願寺住職(ご門主)からいただくものです。
お悔やみの言葉をメールで伝えてもいいの? ―メールで伝えるお悔やみの言葉・例文―
本来なら、訃報の連絡を受けたら、葬儀に参列するか、参列できない場合には電報や手紙を出すのが正式なマナーですが、相手との関係がある程度親密な友人や会社の同僚、仕事関係の取引先など相手と親しい間柄の場合、弔意や励ましの言葉をメールで送っても問題ないとされています。
また、訃報連絡をメールで受けた際は、そのまま返信した方が相手の負担軽減につながります。
その際、メールを送信して終わりではなく、後日直接挨拶に伺ったり、弔電を送ったりして追悼の意を再度伝えるのも大切です。
香典返しとは?時期、金額、品物などのマナーについて解説
「香典返し」とは、通夜・葬儀に参列し、香典を渡した方に送る返礼の品のことです。ただ、一言に香典返しといっても実はいろいろなマナーがあります。この記事では香典返しについての知識、マナーについて解説していきます。
供物とは ―故人を偲び、心を寄せる贈り物―
供物(くもつ)は、故人への気持ちや遺族への弔意を表すために贈る、心を込めて選ぶ故人への贈り物です。
葬儀だけでなく法要の際や、仏様や神様に捧げるものも供物と呼びます。
ここでは、供物について詳しく取り上げます。
お悔やみの言葉の伝え方|言葉の意味やマナー、文例を紹介
「お悔やみの言葉」とは、家族や親族を亡くしたご遺族の方に対してかける言葉のことです。今回の記事では、そのような場面で使われるお悔やみの言葉の意味と使い方、またメール・SNS等を使用したお悔やみの言葉の伝え方、お悔やみの言葉の文例などをご紹介します。
ペット葬とは。大切な家族を供養する、ペット葬をご紹介
大切な家族の一員であるペットが亡くなった時、人間と同じように、火葬・納骨・葬儀を行う人が現代では珍しくなくなっています。
愛するペットとのお別れの時にもきちんと向き合い、送り出してあげるためにも「ペット葬」の基本的な情報をご紹介していきます。
香典袋は何を選べば良い?香典袋の種類や選び方を紹介!
香典とは、葬儀やお通夜、また法事の際に持っていくお金のことです。
その名の通り、死者の霊前に供えるお香に代わる金銭です。
しかし、一言で香典袋といっても、いろんな種類が存在します。
本記事では、そんな香典の種類を紹介します。
遺影とは?葬儀が終わった後、遺影はどこに置く?
遺影とは、故人の写真、またはその姿を写した肖像画などのことをいいます。お通夜や葬儀の際、祭壇に置いて故人を偲んだり、また個人の在りし日を思い起こさせるような式の演出に使われることもあります。
祭壇に置く大きめの写真と、焼香台に置く用の小さめの写真があり、葬儀には欠かせないものです。