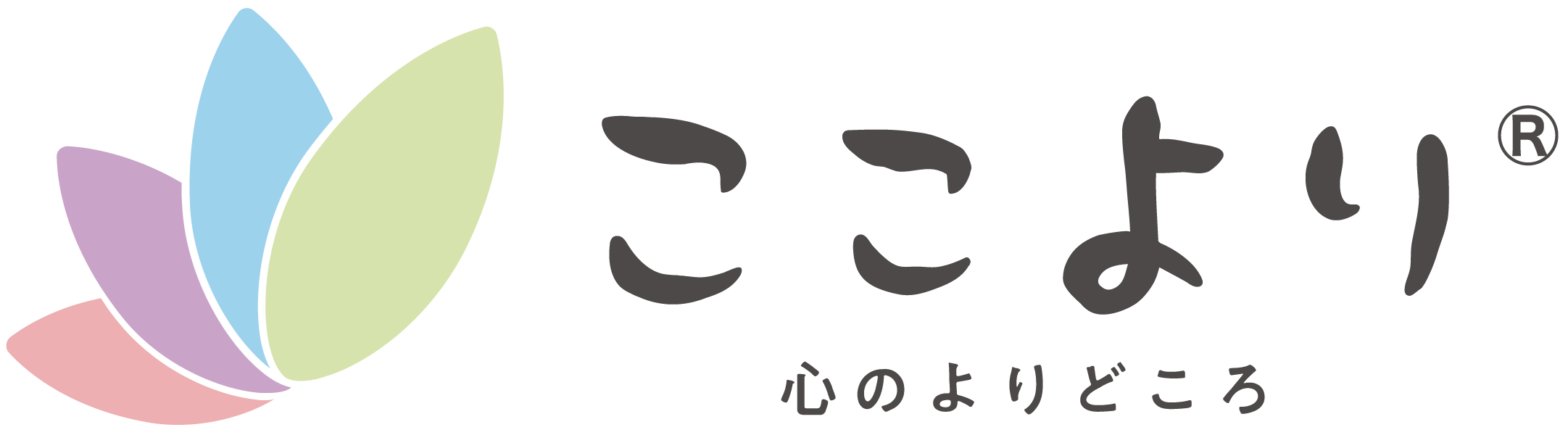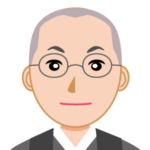目次
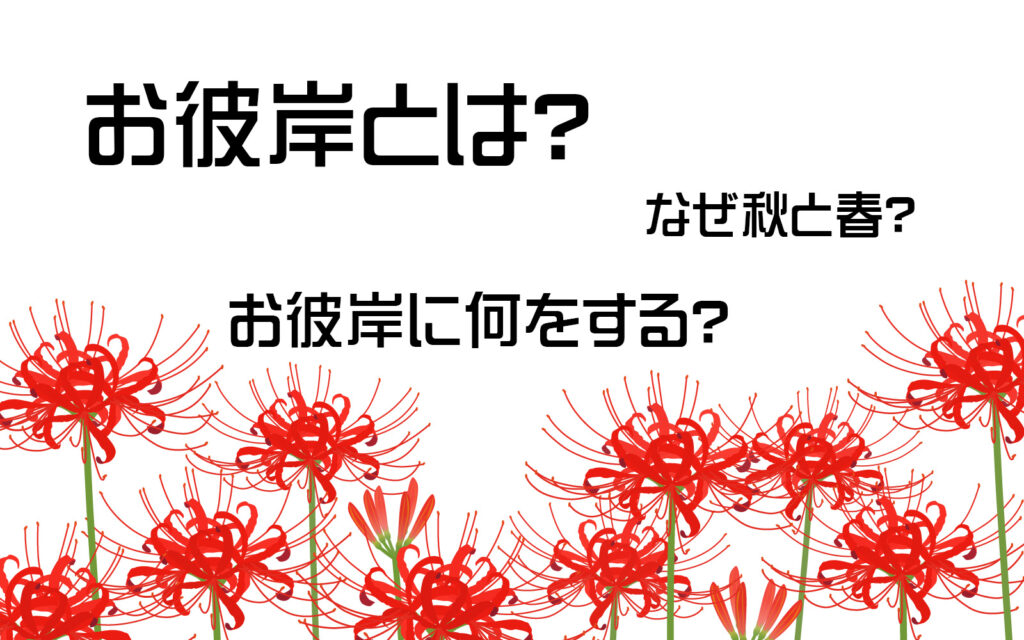
そもそもお彼岸とは?
「お彼岸」とは、日本の仏教で秋分の日と春分の日を中心に前後一週間に行われる仏教行事のことです。
- 秋のお彼岸:秋分の日を中日にして、前後3日間の7日間
- 春のお彼岸:春分の日を中日にして、前後3日間の7日間
この期間に、多くの人がお墓参りに行き、亡くなった家族やご先祖様に感謝の気持ちを伝えます。
「彼岸」と「此岸」って?
私たちが生きているこの世を「此岸(しがん)」と呼びます。
迷いや苦しみに満ちた世界という意味です。
それに対して、仏様が悟りを開いた苦しみのない安らかな理想の世界を「彼岸(ひがん)」と呼びます。
「お彼岸」とは、「迷いの世界から悟りの世界へ渡るために、自分を見つめ直す期間」と考えることができます。
なぜ秋分と春分に行うの?
昼と夜の長さがほぼ同じになる春分の日と秋分の日は、自然界のバランスがとれている特別な日です。
このバランスがとれた日は、心を落ち着けて、仏教の教えを実践するのにふさわしい時期とされてきました。
この時期は太陽が真東から昇り、真西に沈みます。
仏教では、西方に阿弥陀如来の「西方極楽浄土」という悟りの世界があると考えられています。
太陽が真西に沈む光景は、此岸から彼岸へと向かう道筋を示しているのです。
だからこそ、この期間に、仏道修行に励み、亡くなった方々を供養することで、私たちが彼岸に到達できるとされました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
お彼岸に何をする?
お彼岸に行われる主な行いは、次の2つです。
ご先祖供養
お彼岸にはお墓参りに行き、お墓をきれいに掃除して、花やお線香を供え、亡くなった方々やご先祖様に感謝の気持ちを捧げます。
私たちが今ここに生きているのは、ご先祖様のおかげであるという「報恩感謝」の気持ちを表す大切な行為です。
仏壇や仏具をきれいにするのも、仏様を大切にする気持ちを表します。
六波羅蜜(ろくはらみつ)を行う
「六波羅蜜」とは、彼岸、つまり悟りの世界へ渡るための6つの修行のことです。
お彼岸の期間は、これらの修行を特に意識して実践するよい機会とされています。
①布施(ふせ)
見返りを求めず、他者に親切にすること。物を与えるだけでなく、笑顔や優しい言葉も布施です。
②持戒(じかい)
仏教の教え(戒律)や日常のルールを守り、悪い行いをしないこと。約束を守るなどもこれにあたります。
③忍辱(にんにく)
苦難や屈辱、怒りに耐え忍ぶこと。がまん強くなることです。
④精進(しょうじん)
目標に向かって、たゆまず努力すること。勉強や部活を頑張ることも精進です。
⑤禅定(ぜんじょう)
心を落ち着かせ、集中すること。深呼吸や瞑想などもこれにあたります。
⑥智慧(ちえ)
真実を見抜く正しい判断力や洞察力を得ること。物事の本質を考える力です。
おはぎを食べる
おはぎを作って食べる習慣も、仏教と関係があります。
小豆の赤色には魔除けの意味があるとされ、もち米と小豆から作られるおはぎは、五穀豊穣への感謝の気持ちを表すものでもあります。
昔は甘いものが貴重だったので、ご先祖様へのお供え物としても大切にされていました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
お彼岸はご先祖様に感謝し、自分の心を見つめ直す機会
「お彼岸」は、ただの先祖供養の期間ではありません。
仏教の教えに基づいて、ご先祖様に感謝し、私たち自身がよりよい人間になるために、自分の心を見つめ直し、仏道修行に励む、とても大切な行事です。
秋分・春分という自然の節目に、自分や家族、亡くなった方々に思いをはせ、仏教の精神に触れる良い機会でもあります。
皆さんもお彼岸の期間に、ご先祖様に手を合わせ、そして、身近なところから「六波羅蜜」を実践してみてはいかがでしょうか。
家族に優しく接すること、友人の話に耳を傾けること、自分のやるべきことに一生懸命取り組むこと……これらも立派な仏道修行です。
関連記事
許せない人がいる方へ―復讐心を手放してみませんか?|雫有希の「人生 泥中白蓮華」 第4回
「輝け!お寺の掲示板大賞2025」が決定しました!
【折兄さんの食縁日記】第8回 ~ハワイ出張日記~後編
【折兄さんの食縁日記】第8回 ~ハワイ出張日記~前編
2025年度 築地本願寺「報恩講」法要修行のご案内
お葬儀の導師デビュー戦|雫有希の「人生 泥中白蓮華」 第3回

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。
宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!